災害連携の「鍵」はどこにあるのか? - 講演会で得た大きな気づき
災害連携の「鍵」は
どこにあるのか?
- 講演会で得た大きな気づき
本日、午後の診療をお休みさせていただき、三郡市歯科医師航空機災害対策協議会主催の講演会に出席してまいりました。地域の安全を守る活動に貢献するため、皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
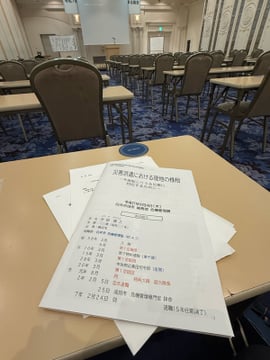
講師は、元陸上自衛官で数々の大規模災害の現場を指揮され、現在は白井市の危機管理官としてご活躍の米田宣久先生です。
東日本大震災をはじめとする過酷な現場経験に裏打ちされたお話は、我々が想定すべき災害のリアルを浮き彫りにするものでした。
温めてきた問いを、現場のプロフェッショナルに私たち歯科医師が災害協力に携わる上で、日頃から私自身が考えていたことがありました。
それは、**「文化も指揮系統も全く異なる組織同士が、あの混乱の中でどうすれば本当に機能するチームになれるのか?」**という問いです。
自衛隊、警察、消防、行政、そして我々医療チーム。それぞれに専門性があり、いわば「常識」も異なります。この根本的な違いを乗り越え、一つの目的に向かうための「鍵」はどこにあるのか。この機会にぜひ専門家のご意見を伺いたいと、事前に質問を用意して臨みました。
(あわせて、近年課題となっている外国人被災者への対応についても質問させていただきました。)
米田先生からいただいた答えは、非常に明快で、かつ本質的でした。
先生が最も強調されたのは、
「互いの組織文化をリスペクトし、決して自分たちのやり方を押し付けないこと」。
そして、その土台となるのが、
「平時からの訓練や協議を通じた『顔の見える関係』づくり」
に他ならない、ということでした。
災害対応という共通のゴールを見据え、普段から「〇〇さん」と呼び合える関係を築いておく。
有事の際に「あの人ならこう動くだろう」と信頼できる関係性をどれだけ作っておけるか。現場の連携は、そうした地道な積み重ねの上にしか成り立たないのだと、改めて胸に刻みました。
歯科医師の専門性を、チームの中で最大限に活かすために
私たち歯科医師の災害時における主な任務は、ご遺体のデンタルチャート(歯科治療の記録)を元にした身元確認作業です。これは非常に専門的な知識を要する重要な役割ですが、決して単独で完結するものではありません。
警察からの情報、行政との連携があって初めて、迅速かつ正確な活動が可能となります。今日の学びは、我々の専門性を地域防災という大きなチームの中で最大限に活かすためには、技術や知識の研鑽だけでなく、他職種への理解とコミュニケーションがいかに重要であるかを教えてくれました。
今後も、地域の一員として、また医療人として、こうした学びの機会を大切にし、防災訓練や協議会へ積極的に参加することで「顔の見える関係」を育んでいきたいと思います。皆様の安全・安心な暮らしを守る一助となれるよう、これからも不断の努力を続けてまいります。

