排便と認知機能の意外な関係:トライアスロン選手の研究から見えてきたこと
# 排便と認知機能の意外な関係:
トライアスロン選手の研究から見えてきたこと

皆さんは「トイレに行った後、頭がすっきりした」と感じたことはありませんか?実は科学的にも、排便と頭の働きには関係があるかもしれないという興味深い研究が発表されました。今回は高校生の皆さんにも理解しやすいよう、この最新研究を解説します。
## どんな研究だったの?

台北大学の研究チームが行った実験では、13人のエリートトライアスロン選手に参加してもらい、「排便した後」と「排便していない状態」で脳の働き(認知機能)がどう変わるかを調べました[1]。
実験では3つの条件を比較しました:
1. 排便なしの状態
2. 自然に排便した後の状態
3. マグネシウムのサプリメントを飲んで排便した後の状態
各条件間には1週間の間隔を設け、食事や水分摂取を統制しました[1]。脳の働きを調べるために「ストループテスト」という、色の名前と実際の色が一致しないときにどれだけ正確に答えられるかを測る検査が使われました[2,4]。例えば「赤」という文字が青色で書かれているとき、色(青)を答える必要があります。
## 驚きの結果:排便後は頭の回転が速くなる?
研究結果は興味深いものでした:
- **排便後は脳の働きが良くなる**: 排便していない時と比べて、排便後はストループテストの成績が向上しました(完了までの時間が短縮)[1]
- **特にマグネシウム排便が効果的**: 単に自然に排便した時よりも、マグネシウムを摂取して排便した後の方が、さらに良い結果が出ました[1,3]
- **具体的な数字では**:
- 排便なし:27.1秒
- 自然排便後:24.4秒
- マグネシウム排便後:23.4秒
また、排便後は腹部の酸素消費量が増えていることもわかりました[1,6]。これは腹部(腸)が認知課題を行っている間も活発に働いていることを示しています。
## なぜ排便が脳に影響するの?
実は私たちの腸には「腸管神経系」と呼ばれる神経のネットワークがあり、これは「第二の脳」とも呼ばれています[3,7]。脳と腸は「腸脳相関」と呼ばれる仕組みで常に情報をやり取りしているのです。
つまり:
- 便秘などで腸に負担がかかると、脳の働きにも影響が出る可能性がある
- 逆に、排便によって腸の負担が減ると、脳の働きが改善する可能性がある
過去の研究でも、便秘が認知症患者の思考能力を低下させることや、腸内の細菌バランス(腸内フローラ)が認知機能に影響することが示されています[3,7]。実際、2023年に発表された研究では、排便パターンと認知機能の間に関連があることが報告されています[3]。
## この研究の限界:うーん、でもちょっと待って
興味深い結果ですが、Wei氏らの研究にはいくつか注意点もあります:
1. **対象者が少なく特殊**: わずか13人のエリートトライアスロン選手だけが対象[1]。一般の人にも同じ効果があるかはわかりません。
2. **短期的な効果だけを見ている**: 長期的に見たらどうなのか、日常的な排便習慣との関係はまだ調査されていません[1,3]。
3. **腸内細菌の影響は未検証**: 腸内の細菌バランスが結果にどう影響しているかはわかっていません[3,7]。
4. **因果関係がはっきりしない**: 排便そのものが認知機能を高めたのか、それとも単に「すっきりした気分」が集中力を高めただけなのかもわかりません[1,3]。
## 今後の研究でわかるといいこと
今回の研究は面白い可能性を示しましたが、まだ初期段階です。今後は以下のような研究が期待されます:
- より多くの一般的な人々を対象にした研究
- 子どもからお年寄りまで、様々な年代での効果検証
- 腸内細菌と認知機能の関係のより詳しい調査[7]
- 長期的な排便習慣と脳の健康の関係
## 日常生活への応用:トイレをガマンしない!
この研究からすぐに「排便で頭が良くなる!」と結論づけるのは早計ですが、少なくとも「トイレに行きたいときはガマンしない方が良い」と言えそうです。トイレをガマンすると、本来集中できるはずの脳のリソースが「ガマン」に使われてしまうかもしれません。
また、マグネシウムを含む食品(ナッツ類、豆類、緑黄色野菜など)をバランスよく摂ることも、腸の健康に役立つかもしれません[8]。マグネシウムは腸の動きを活発にし、便通を改善する効果があることが知られています。
## まとめ:腸と脳の不思議な関係
私たちの体は様々な器官が複雑につながり合っています。今回の研究は「腸と脳のつながり」について新たな視点を提供してくれました。まだ研究途上の分野ですが、日々の排便習慣が思考力や集中力に影響する可能性は十分考えられます。
「腸内環境を整えることは、脳の健康にもつながる」—この考え方は、フロンティアズ・イン・パブリック・ヘルス誌に掲載された最近の研究[7]でも支持されており、今後の健康管理においてさらに重要になってくるでしょう。
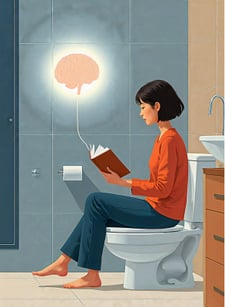
## 参考文献
[1] Wei, C.-C., et al. (2024). *Defecation after magnesium supplementation enhances cognitive performance in triathletes*. Sports Medicine and Health Science, 6(2), 147–152.
[2] デジタルスタンダード公式. (2023). *ハカロシリーズ ストループテスト*. https://digital-standard.com/hst_jp/
[3] PubMed. (2023). *Association Between Bowel Movement Pattern and Cognitive Function*. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37775319/
[4] パリアティブケアホーム. (2023). *TMT検査とストループ検査について*. https://palliative-care-home.com/column/p1522/
[5] Biomarkers of cognitive and memory decline in psychotropic drug. (2024). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11735527/
[6] 九州大学. *新ストループ検査は注意機能の臨床評価ツールとなりうるか?*. https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/26128/p001.pdf
[7] Frontiers in Public Health. (2024). *Trajectories and influencing factors of cognitive function*. https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2024.1380657/full
[8] 消費者庁. *表示しようとする機能性の科学的根拠に関する補足説明資料*. https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc06/youshiki5?yousiki5216File=E709%255CE709_youshiki5.pdf

